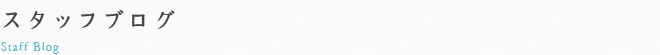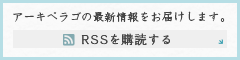今回の旅の水先案内人は、地元高松で革新的な活動を続ける栗生さん。島々を渡り歩くなか豊島と出会い、豊島に恋をした彼女は、今、豊島に毎週通う。多島海と恋をする彼女から旅のガイダンスを受けた後、乗船。最初に向かうのは小豊島、高松からの定期航路はない。豊島フェリーさんが用意下さったチャーター船での渡航となった。
小豊島は、牛の島だ。島の人口の何倍もの頭数の肉牛を飼い、生計を立てて来た人々が暮らしている。島に牛を運び、暮らしを支えて来たのが舟だ。すこし前まで、舟は木で出来ていた。木を加工し、舟を造ってきた舟大工の夫婦が、この島に暮らしている。出迎えてくれた奥さんに案内いただきながら、小さな集落を歩く。軒先の様子から、シンプルで無駄のない、きれいな暮らしがあることがわかる。廃校脇の公民館で、僕らはとびっきりの昼食と、あたたかいお茶をいただいた。
舟大工の竹内さん、85歳。木の舟を造って来た船小屋も、作業台も、イスも、全て木で出来ていた。ザクロが揺れる工房で、僕らは寡黙な竹内さんが少しずつ語る言葉に耳を傾ける。先代と作った舟の話、木に替わった新素材の話、そして舟の守り神「舟魂さん(ふなだまさん)」話。目の前で舟魂さんを造る竹内さんは無口のままだけど、作業は確実だった。「イッテンチロク、ミヨシミアワセ、トモシアワセ・・・」呪文のようにつぶやきながら、丁寧に舟魂さんを仕上げる。その言葉の意味は何ですかと問えば、「無理すんなってこっちゃ。無理しなきゃ、みんなが幸せってこっちゃ。」と、竹内さん。「お父さんは、ごそごそ仕事するのが好きなん。」と、奥さん。船小屋の中にある使い込まれた道具たちは、出番を待っているように見えた。庭先には、息子さんが採って来たという大きな貝の貝殻が、誇らしげに干してあった。
豊島に渡った僕らは、栗生さんが港に開いたバール「HITAKI」へ。イチゴ屋さん!と親しまれる島一番のイタリアンシェフがパスタを作ってくれた。小豊島帰りの腹ぺこな僕ら、その目の前に島のオリーブが贅沢に使われた柚子の香りのペペロンチーノ。競うように箸を延ばし、うまいうまいと食べる。冷えたワインが有り難かった。食事の後、ストーブを囲むように皆でイスを並べた部屋で、島の人を囲んで話し込む。島のお祭りの話、結婚の話、葬儀の話、おのろけ話もあったかな。餅つきの時に掛け合いで歌う「祝いの歌」が出てからは、歌合戦。島に伝わる「締めの歌」で、宴はひとたび幕を閉じた。また来たい、また会いたい。そう思ってしまう、この人のあたたかみは何だ。
旅は2日目、栗生さんの基地「ブワナアユ甲生(こう)別館」での朝。彼女の手料理で朝ご飯。ウニと椎茸のスープの味が忘れられない。支度を済ませ出発、皆で集落を散策、島の旧家「片山邸」へ。荘厳なお屋敷を拝見しながら、この島の歴史に意識が向かって行く。お茶をいただき、この島に似つかわしくないほどの細やかな造形に目をやりながら、かつてこの島を愛し、この島のために矢面に立った人の存在や、この家の主と住民との共同体の存在を感じずにはいられなかった。
片山邸を後にして、僕らは石井さんの車で豊島の最高峰・壇山に登った。石井さんは、この多島海では知らない人のいない革命家(だと僕は思っている)だが、現在はこの島で「ヤギとハナバタケ社」という観光案内会社を営んでいる。山頂からは、瀬戸内の多島海が箱庭のように見えた。ゆっくりと進む船の存在が、それが絵画ではないことを思い出る。1000年スケールで語られる島の歴史は、日本人の記憶とオーバーラップするようで、脳が揺れる。最高峰は水瓶の役割も果たし、豊かな森を育み、泉が湧き、作物をもたらした。この島は、長い間、生物にとって豊かな島であったのだろう。豊かな島と書いて豊島、ということか。
壇山から降りて、島のイートイン総菜屋「うらら」へ。「鴨を打って来たらしいから!」と、この日に猟師が射止めた島の鴨を大胆に調理した鴨鍋。雑魚を背開きにし、酢飯を詰めた豊島キュイジーヌ。島の猟師、漁師、ご近所さんとの不断のつながりが、この豊かな食卓に結実しているのだろう。気さくな奥さんがテンポよく料理を説明し、話はご夫婦の馴れ初めにまで。「お父さんがポケットに入れてくの。甘い物が好きだから・・・」大切な干し柿をいただきながら、僕らはまた、あたたかい気持ちになった。
そして僕らは、近代豊島の震源地へと向う。案内いただいたのは、廃棄物対策豊島住民会議の元議長の砂川さん。砂利道を走り、バスが到着したのは廃棄物投棄現場、現在は処理施設がある島の海岸だ。海を渡って島にもたらされた廃棄物、それとき合って来た島の人たちの半生がここにある。行政主導での処理が始まった今、砂川さんは一歩ひいて様子を見つめる。循環型社会実現に向けたモデル事業とまで謳う処理施設の広報ビデオのことは置いておき、今回僕が初めて知ったのは、施設を紹介してくれる県職員の方が、実は、かつての島の有志の娘さんだと言うことだ。かつて島と行政は争った。そして今、島を代表したメンバーの娘さんが、行政の施策の説明る。背景や立場を背負いながら、それでも中立的に説明する彼女に、僕はビックリした。そこに感じたのは、人間の持つ寛容性であり、歴史の持つ自己治癒力なのかもしれない。世代を超えて怒りや憎しみを持ち越さないことができた時、世界は少しだけ変化するのだろう。心の資料館に場所を移し、砂川さんの言葉を聞く。大きな白い紙には戦友たちの名前が刻まれ、黒い点に見えるは喪章だ。「次は自分の番だ。」という砂川さんは、とてもきれいな顔をしていた。「豊かなふる里、わが手で守る」と書かれたり紙と、イスに腰掛け、当時を語りながら震える砂川さんの手が、僕の中で静かに結びついた。彼らは、この島を守ろうとした。自分のためにではなく、未来の島民のために。 ふる里とは、つくるものだろう。
産廃投棄現場の隣にある静かな入り江、その海辺に建つヨットハーバー・アモーレ豊島リゾート、3日目の朝。隣の小豊島では、舟大工の竹内さんご夫婦が朝仕事を始めたかもしれない。隣の入り江では、今日も産廃処理施設が稼働する時間だろう。隣にある存在、そのまた隣にある存在。お互いがお互いの存在に配慮しながら、それぞれの思う最善を尽くしている世界が、ここにはあった。多島海というフィールド悠久の時間の流れの中で、人間の営みや自然との共生は、ごくごく自然に育まれ、侵した過ちや、それによって負った傷さえも治癒しながら、緩やかな関係性と共同性がつむがれ続けている。
知らなかったことを一つ知り、まだ知らないことがあることも知る。栗生さんたちに手を振り、僕らはまた、それぞれの旅に向かった。瀬戸内の多島海は、11月でもあたたかい。
(文責/イシクラ)